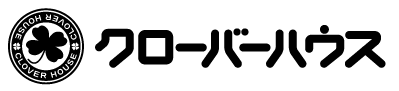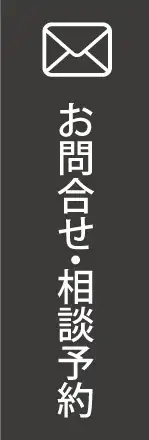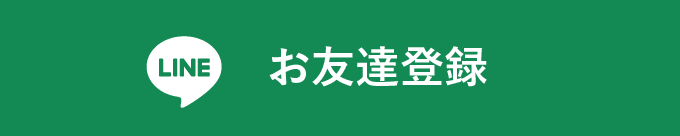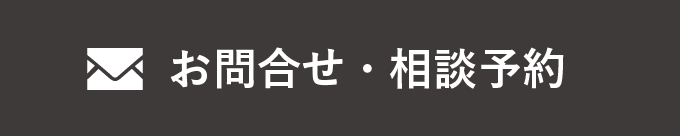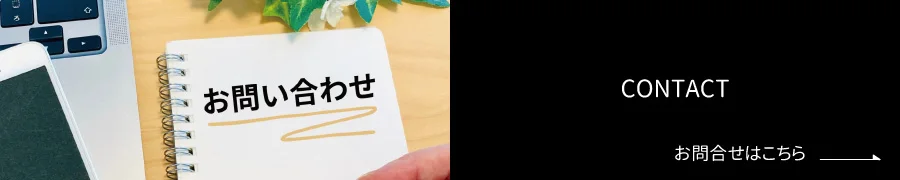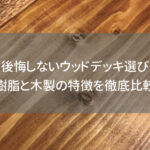NEWS&BLOG
ニュース・ブログ
2025.07.15|ブログ
安心できる中古マンション選び!リノベーションで叶える耐震性と快適な暮らしの秘訣
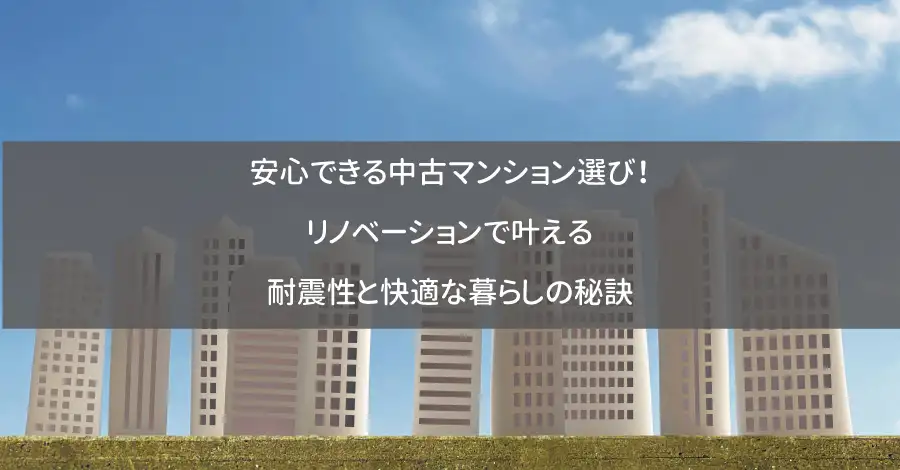
中古マンションリノベーションで最も気になる「耐震性」の真実
大阪や北摂エリアで、中古マンションの購入を検討し、自分らしい空間へとリノベーションを夢見ている皆様。
数ある検討ポイントの中でも、きっと真っ先に頭に浮かぶのが「このマンションの耐震性は大丈夫だろうか?」という不安ではないでしょうか。
愛着あるマイホームで長く安全に暮らすためには、建物の耐震性能は非常に重要な要素です。
しかし同時に、この「耐震性」については、様々な誤解や間違った認識が生じやすいのも事実です。
築年数だけを見て「古いから危ない」と決めつけてしまったり、逆に「新しいから安心」と過信してしまったりすることもあります。
実際には、一概に築年数だけで耐震性を判断できるものではありません。
建物の構造、設計、そして何よりも「日々の管理状態」が、そのマンションの耐震性や寿命に深く関わってきます。

この記事では、中古マンションの耐震性に関する「よくある質問」を一つずつ丁寧に解説していきます。
耐震基準の変遷から、耐震・免震・制振といった地震対策の種類、そして築年数以外に確認すべき重要ポイントまで、専門的な知識を分かりやすくお伝えします。
あなたのリノベーション計画が、単なるデザインの追求だけでなく、安心して暮らせる安全な住まいを実現するための確かな一歩となるよう、ぜひ最後までお読みください。
戸建て vs. マンション:耐震性能はどちらが優れているのか?
「マンションの方が、地震に強い」
漠然とそう考えている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、一戸建てとマンションの耐震性能を比較する際には、いくつかの視点から考える必要があります。

構造と設計による違い
マンション(RC造・SRC造)
多くのマンションは鉄筋コンクリート造(RC造)や鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)で建てられています。これらの構造は、コンクリートと鉄筋(または鉄骨)を組み合わせることで、非常に高い強度と粘り強さを持っています。
戸建てに比べて自重が重いため、地震の揺れを大きく感じやすいという側面もありますが、建物全体の剛性が高く、倒壊に至るリスクは低いと考えられています。
一般的に、高層建築物では、地震の揺れを効率的に逃がすための設計(免震構造や制振構造)が採用されていることも多く、その場合はさらに高い耐震性を誇ります。
一戸建て(木造)
木造住宅は、木材のしなやかさを活かした構造であり、地震の揺れを吸収する能力を持っています。
適切な設計と施工、そして定期的なメンテナンスが行われていれば、現在の耐震基準を満たした木造住宅は、地震に対して十分な強度を持っています。
ただし、木造一戸建ての場合、地震の際に建材が破損したり、家具が転倒したりすることによる「飛び火」の問題や、シロアリによる木材の劣化が耐震性に影響を及ぼす可能性も考慮する必要があります。これらの対策は、定期的な点検と適切な修繕が不可欠です。
建物の平均寿命から見る耐久性
建物の耐用年数や寿命も、耐震性と同様にその耐久性を示す指標となります。早稲田大学の小松幸夫教授らの調査によると、建物の平均寿命は以下のようになっています。
・RC/鉄筋コンクリート造マンション: 約68年
・木造住宅: 約64年
このデータを見ると、わずかではありますがRC造のマンションの方が平均寿命が長いことが分かります。
これは、コンクリートと鉄筋の組み合わせが、木材に比べて物理的な劣化が遅いことや、維持管理が行き届きやすい集合住宅という特性も影響していると考えられます。
結論として、「きちんとした設計・構造であれば、一戸建てでもマンションでも問題なく高い耐震性能を持つことができる」と言えます。
どちらが一方的に優れているというよりは、それぞれの構造の特性を理解し、個々の物件がどのような基準で建てられ、どのように維持管理されてきたかを見極めることが重要です。
特に大阪や北摂では、過去に大きな地震を経験している地域でもありますので、物件選びの際には構造の特性を理解し、専門家のアドバイスを仰ぐことを強くお勧めします。
「新耐震基準」以降の建物は本当に安全?基準の変遷とマンション選びのポイント
中古マンションの耐震性を語る上で、最も重要なキーワードとなるのが「新耐震基準」です。
この基準が何を意味し、なぜ重要なのかを理解することは、安心して物件を選ぶための第一歩となります。
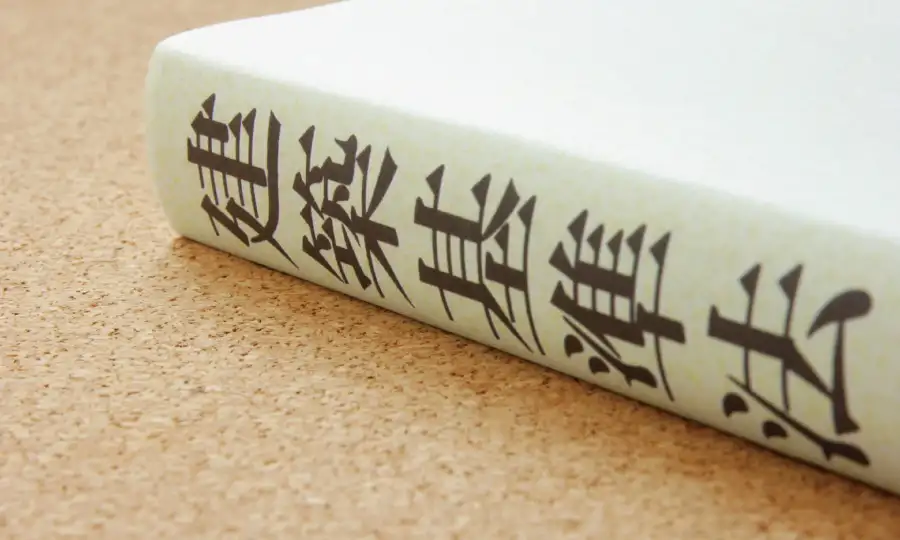
日本の耐震基準の歴史と「新耐震基準」の誕生
日本の建築物の耐震基準は、過去の大地震の教訓を経て、幾度となく改正が繰り返されてきました。
・1923年 関東大震災
・1948年 福井地震
・1968年 十勝沖地震
・1978年 宮城県沖地震
これらの大地震が発生するたびに、建築基準法は新しい基準の制定や改正を重ねてきました。
中でも、特に大きな改正として位置づけられているのが、1981年(昭和56年)6月1日に施行された建築基準法の大改正です。
これが一般的に「新耐震基準」と呼ばれています。
「新耐震基準」が定める強度とは
1978年の宮城県沖地震(死者27人、建物の全半壊7500戸という甚大な被害を宮城県内で記録)を教訓に、新耐震基準は、住宅やマンション・ビルなどの建築物に対して、以下の強度を義務付けました。
・震度5強程度の中規模地震:建物の軽微な損傷にとどまること
・震度6強から7程度の大規模地震:倒壊や崩壊は免れること
これにより、大規模地震が発生しても人命を守ることを最優先とした、新たな設計基準が設けられたのです。
新耐震基準の有効性と阪神・淡路大震災
新耐震基準の有効性は、1995年に発生した阪神・淡路大震災において、ある程度証明されたと言われています。
国土交通省の公式サイトにも「阪神・淡路大震災では、住宅・建築物の倒壊による大きな被害が見られた」とする中で、「特に新耐震基準が導入された昭和56年(1981年)以前に建築されたものに大きな被害が発生」と明確に記されています。
これは、新耐震基準以降に建てられた建物が、旧耐震基準の建物に比べて、地震による倒壊の被害を大きく軽減できたことを示唆しています。
「新耐震基準以降」のマンションを選ぶべきか?
では、「どちらがより安全か」と問われれば、統計上は「新耐震基準以降に建てられたマンション」ということになります。
しかし、一方で、それ以外の建物(旧耐震基準の建物)が全て安全ではないと言い切ることもできません。
築40年を超えるマンションの中にも、耐震構造的に高いレベルで安全性を確保しているものが存在します。
旧耐震基準で建てられたマンションであっても、その後に耐震診断を行い、新耐震基準をクリアする耐震性が認められたものもあります。
さらに、耐震改修や耐震補強工事を積極的に実施しているマンションも多数あります。
中古マンションの価格は、築年数が非常に大きく影響する要素です。新耐震基準以降のマンションは、旧耐震基準のマンションに比べて価格が高めに設定されている傾向があります。
どの時期のマンションを購入すべきかについては、最終的には「購入される方の考え方次第」ということになります。
「多少費用がかかっても、統計的に安心できる新耐震基準以降のマンションがいい」と考える方もいれば、「旧耐震基準のマンションでも、耐震診断や補強の履歴があれば価格を抑えてリノベーションしたい」と考える方もいるでしょう。
大阪や北摂で中古マンションを探す際には、単に築年数だけでなく、そのマンションがどのような耐震対策を講じてきたか、そしてこれからどのような計画があるのかをしっかりと確認することが賢明です。
耐震・制振・免震:地震対策の3つの違いを理解する
現在の住宅建築における地震対策は、主に「耐震」「制振」「免震」の3つに分類されます。
これらの違いを理解することは、マンションの地震対策レベルを判断する上で非常に役立ちます。

この3つの違いは、地震により発生する振動エネルギーが建物に伝わるのを「いかに防ぐか」「どのように受け流すか」「どのように吸収するか」という、その防ぎ方の違いにあります。
耐震構造:揺れに「耐える」強さ
定義:建物自体を非常に頑丈なつくりにすることにより、地震の揺れによって建物が壊れないようにすることを目指す手法です。地震の揺れを防ぐための特殊な付属装置は使いません。
仕組み:建物の骨組み(柱や梁など)を強化したり、建物の躯体(コンクリート壁や床スラブ)に筋交い(柱と柱の間に斜めに入れて構造を補強する部材)や補強金物などを効果的に用いることで、地震の揺れに対する耐久性(粘り強さや強度)を高めます。
特徴
最も一般的な地震対策であり、日本の多くの建築物で採用されています。
建物自体が揺れに抵抗するため、建物内部の揺れは比較的小さく抑えられますが、揺れ自体は直接建物に伝わります。
コスト面では、免震や制振に比べて比較的安価に実施できるため、既存住宅の耐震補強でも多く採用されています。
注意点:建物自体は倒壊を免れても、家具の転倒や内装材の損傷は発生しやすい傾向があります。そのため、建物内部の家具固定などの対策も併せて行うことが推奨されます。
制振構造:揺れを「吸収する」しなやかさ
定義:建物の要所要所に、地震の揺れによるエネルギーを吸収する特殊な装置(制振ダンパーなど)を備えることで、建物の揺れを抑える手法です。
仕組み:地震時に発生する建物の変形や揺れを、制振装置(オイルダンパー、粘性ダンパー、履歴型ダンパーなど)に吸収させることで、地震エネルギーを熱などに変換し、建物に伝わる揺れを少なくします。まるで建物の「サスペンション」のような役割を果たします。
種類
パッシブ制御(受動的制御):ダンパー自体が地震の揺れによって自動的にエネルギーを吸収するタイプです。動力源を必要としません。
アクティブ制御(能動的制御):油圧や電気などの動力を用いて、揺れを能動的に制御するタイプです。大きな振り子のような装置が知られています。
特徴
耐震構造と組み合わせて採用されることが多く、建物の損傷を軽減しつつ、居住者の揺れに対する恐怖心を和らげる効果が期待できます。
比較的コストは免震構造よりは抑えられますが、耐震構造よりは高価になります。
高層マンションや、特に長周期地震動対策として有効とされています。
実は、日本古来の建築物である五重塔なども、揺れを建物全体で吸収する、ある種の制振構造を備えていると言われています。
免震構造:揺れを「伝えない」柔らかさ
定義:建物を地面や基礎から物理的に切り離し、地震の揺れが建物に直接伝わらないようにすることを目指す手法です。
仕組み:建物と地盤の間に、積層ゴムアイソレーター(ゴムと鋼板を何層も重ねたもの)や滑り支承(すべりじしょう)などの特殊な免震装置を設置します。これにより、地震の水平方向の揺れを建物に伝わりにくくし、建物自体の揺れを大幅に低減します。
特徴
地震の揺れを建物に「伝えない」ため、建物内部の揺れが非常に小さく抑えられます。これにより、建物の損傷だけでなく、家具の転倒や内装材の被害も大幅に軽減できる可能性が高いです。
揺れが少ないため、地震発生時にも居住者の安全性が高く、建物内部の設備やインフラへの影響も抑えられます。
比較的コストが高く、敷地面積も必要となるため、新築の超高層マンションや重要な公共施設などで採用されることが多いです。既存マンションへの後付けは非常に困難です。
コストと選択肢:中古マンションと地震対策
コスト面で言えば、工事工程が複雑な「免震」や、高価なダンパーを利用する「制振」は、「耐震」と比べると建築コストが高めになります。
そのため、現在の既存住宅の地震対策は、コストの問題もあり「免震」や「制振」よりも、「耐震」構造が一般的です。
専門家の中には、1981年以降につくられた「新耐震基準」で建てられた建物であれば、建物内部の家具固定などの地震対策をしっかり行っておくことで、「耐震」構造でも十分な安全性が確保できるという意見もあります。
大阪や北摂で中古マンションを選ぶ際は、そのマンションがどのような地震対策(耐震、免震、制振)を講じているかを確認し、ご自身の安心レベルと予算に合わせて選択することが重要です。
築年数以外にチェックすべき!中古マンションの「管理状態」が耐震性に及ぼす影響
中古マンションの耐震性を判断する際、築年数や構造の種類だけでなく、「マンションの管理状態」も非常に重要な要素となります。
これは、築年数と同じくらい、あるいはそれ以上に重要であるにもかかわらず、見落とされがちなポイントです。

マンションは、大切に維持管理されていれば、非常に丈夫な状態で長持ちします。
しかし、逆に管理の不徹底が、建物の劣化を早め、最終的には耐震性能にまで悪影響を及ぼすケースも少なくありません。
例えば、雨漏りを放置すれば躯体内部の鉄筋が錆び、コンクリートが脆くなる原因となります。
外壁のひび割れを放置すれば、そこから雨水が侵入し、構造材を傷める可能性があります。
そのため、定期的な修繕が適切に行われているか、そして将来に向けた修繕計画がきちんと立てられているかを事前に確認することが、安心して中古マンションを購入し、リノベーションを進める上で非常に重要です。
修繕履歴や計画の確認方法
不動産会社を通じて管理組合へ依頼
気に入ったマンションが見つかったら、不動産会社を通じてマンションの「管理組合」に連絡を取り、以下の書類の開示を依頼しましょう。
長期修繕計画書:今後、何年スパンでどのような修繕工事が計画されているか、その費用がどのように賄われるかなどが記載されています。
修繕履歴:過去にどのような修繕工事(外壁塗装、屋上防水、給排水管の更新、耐震補強など)が行われたかの記録です。
総会議事録:管理組合の運営状況や、住民間の問題意識、修繕積立金の見直し履歴などが分かります。
書類から読み取るポイント
計画の具体性:長期修繕計画が具体的に作成され、定期的に見直されているか。
計画の実施状況:計画通りの修繕がきちんと実施されているか。
資金計画の健全性:修繕積立金が十分に積まれているか、急な値上げの予定はないか、管理組合に大きな借入はないか。
住民の意識:総会議事録から、住民全体の管理に対する意識の高さや、問題解決に向けた取り組み姿勢を読み取ることができます。
目視による管理状態のチェックポイント
書類での確認だけでなく、実際に物件内見の際に、ご自身の目で「管理状態」をチェックすることも非常に有効です。
外装・共用部
外壁:ひび割れ、タイルの剥がれ、塗装の劣化などがないか。
エントランス・ホール:清掃が行き届いているか、照明は切れていないか、植栽は手入れされているか。
エレベーター:清潔か、異臭はしないか、メンテナンス表示は適切か。
廊下・階段:清掃状態、手すりのガタつき、照明の有無。
ゴミ置き場:清潔に保たれているか、ゴミが散乱していないか。
駐車場・駐輪場:整理整頓されているか、適切な管理がされているか。
植栽:枯れている植物がないか、定期的に剪定されているか。
設備
給排水管の老朽化が疑われる場合、共用部から錆汁の跡がないか、排水溝に詰まりやすいゴミが散乱していないかなどもチェックポイントです。
目視によるチェックだけでも、そのマンションが日頃からどれだけ大切に手入れや修繕を行っているか、ある程度の雰囲気を掴むことができます。管理が行き届いているマンションは、住民の管理意識も高く、将来的な維持管理も安心できると言えるでしょう。
特に大阪や北摂のマンション市場では、築年数が経っていても管理状態の良い物件は資産価値を維持しやすい傾向にあります。
耐震補強されていれば安心?修繕・補強履歴と計画を見る上での重要ポイント
中古マンションの購入を検討している中で、「このマンションは耐震補強工事済みです」という情報に触れることもあるでしょう。
耐震補強がされていることは安心材料ですが、その内容を深く理解することが重要です。

耐震補強工事の内容を深掘りする
単に「耐震補強工事を実施した」という事実だけでなく、「どういった補強を施したのか」そして「最終的にどの程度の強度になっているのか」が最も重要です。
補強内容の確認
具体的な補強方法(例えば、耐震壁の増設、既存の柱や梁への炭素繊維シート巻き付け、基礎の補強、制振ダンパーの設置など)を確認しましょう。どのような地震対策がされているかを知ることで、そのマンションの安全性レベルをより正確に把握できます。
新耐震基準適合の有無
特に重要なのが、耐震補強工事を行った結果、現行の「新耐震基準」に適合しているかどうかです。マンションによっては、耐震補強工事をおこなったものの、完全に新耐震基準を満たしていない場合があります。現行の基準を満たしていることは、安全面だけでなく、購入後に住宅ローン控除や不動産取得税の軽減といった税制優遇の対象となるかどうかにも大きく影響します。
専門家による確認
耐震補強されたマンションを購入する場合も、購入前にリノベーション会社や一級建築士などの専門家に、どの程度の補強がされ、どのような効果が期待できるかを確認してもらいましょう。必要であれば、そのマンションの耐震診断報告書や改修計画書の内容を詳しく見てもらうのが確実です。
マンションの場合、耐震診断や耐震補強という取り組みを個人で勝手に行うことはできません。そのため、マンション全体の管理組合による耐震に関する意識の高さと、それに基づいた取り組みがより大切になります。
長期修繕計画の綿密な確認
耐震補強の履歴がある・ないに関わらず、中古マンション購入前に必ず確認しておきたいのが「長期修繕計画」です。
これは、そのマンションの将来的な安心感と資産価値に直結する非常に重要な書類です。
計画の内容
外壁の塗り替え、屋上防水、給排水管の更新、エレベーターの改修など、今後数十年間にわたって行われる大規模な修繕工事の具体的な内容、実施時期、必要な費用が詳細に記載されています。
定期的な見直し
長期修繕計画は、一度作ったら終わりではありません。建物の劣化状況や法改正、住民のニーズの変化に合わせて、定期的に見直され、更新されているかを確認しましょう。見直しの頻度が低い、または全く見直されていない場合は、計画が現実的でない可能性があります。
日常的な管理状態からの推測
書類だけでなく、実際にマンションを内見する際には、エントランスやホール、植栽、ゴミ置き場などの共用部の状態を注意深くチェックすることをおすすめします。これらがきちんと手入れされているマンションは、管理組合の意識が高く、長期修繕計画も適切に実行されている可能性が高いと推測できます。
修繕積立金を含む資金計画の健全性
長期的な修繕の予定だけでなく、それらの工事に必要となる「資金計画」が適切になされているかも非常に重要な確認ポイントです。
修繕積立金の見直し
修繕積立金は、新築時から一定額であるとは限りません。建物の経年劣化や大規模修繕の時期に合わせて、金額が見直されるのが一般的です。その見直しが、修繕計画に合わせて現実的に行われているかを確認しましょう。
資金不足のリスク
万が一、大規模修繕工事の直前まで資金不足が認識できていない場合、急遽、修繕積立金の大幅な値上げが発表されたり、管理組合が金融機関から高額な借り入れをせざるを得なくなったりと、想定外の出費や負担が発生する可能性があります。 これは、将来の家計に大きな影響を与えます。
管理組合の財政状況
総会議事録や会計報告書を確認し、修繕積立金の積立状況、管理費の滞納状況、管理組合の負債の有無など、財政状況の健全性を把握しておくことが大切です。
大阪や北摂で安心して暮らすために、中古マンションの耐震性は、築年数だけで単純に判断することはできません。物件購入前に、上記のポイントをしっかりと押さえて確認しましょう。中古マンション選びは、単に部屋の広さやデザインだけでなく、マンション全体の「管理状態」や「長期的な計画」といった物件の本質を深く見極めることが、成功と安心の鍵となります。
まとめ:北摂で安心のリノベーションを叶えるために
大阪や北摂で中古マンションのリノベーションを検討する際、「耐震性」は最も重要な要素の一つです。
しかし、この記事で見てきたように、耐震性を判断するには、単に築年数だけを見るのではなく、より多角的な視点が必要です。

・建物の構造特性(RC造、SRC造、木造など)を理解し、それぞれのメリット・デメリットを把握すること。
・「新耐震基準」が導入された1981年以降の建物であるかどうか、そして旧耐震基準の建物であっても、耐震診断や耐震補強が適切に行われているかを確認すること。
・地震対策の種類である「耐震」「免震」「制振」それぞれの仕組みと特徴を理解し、物件の地震対策レベルを把握すること。
・そして何よりも、マンションの「管理状態」が良好であるか、そして「長期修繕計画」と「資金計画」が健全であるかを徹底的に確認すること。
これらのポイントをしっかり押さえることで、単に希望の間取りやデザインを実現するだけでなく、将来にわたって安心して快適に暮らせる、安全な中古マンションを賢く選び、リノベーションを成功させることができます。
大阪や北摂の地域に根差した私たちクローバーハウスは、中古マンションの物件探しから、耐震性を含めた物件診断、リノベーションの設計・施工、そして資金計画まで、ワンストップで皆様をサポートいたします。
「このマンションはリノベーションでどこまで変わる?」「耐震性は大丈夫?」など、どんなご不安や疑問でも、どうぞお気軽にご相談ください。
専門家として、皆様が納得のいくリノベーションを実現できるよう、誠心誠意お手伝いさせていただきます。
クローバーハウスは、大阪・北摂地域での新築、建て替え、リフォーム・リノベーション、住まいの事なら何でもご相談いただけます!
耐震診断、住まいのインスペクションなどもお気軽にご相談ください。
大阪・北摂エリアでの中古物件探しからリノベーションまで、ワンストップでご相談いただけます。お気軽にお問い合わせください。
物件探し×リフォーム・リノベーションをワンストップでご提案
家を探す。買う。リノベーションする。
理想の暮らしを北摂で。
クローバーハウス Clover house
大阪府吹田市金田町5-19
大阪・北摂エリア:吹田市・豊中市・箕面市・淀川区・東淀川区
→電話でお問合せ
→メールでお問合せ
→LINEでお問合せ
→相談予約
→資料請求